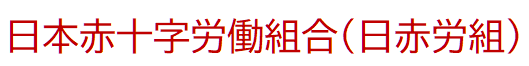執行委員長あいさつ
日本赤十字労働組合
中央執行委員長
佐々木 伸樹(ササキ ノブキ)
年末年始において各職場で勤務に就かれた組合員の皆さん。昨年の2月から2024春闘として取り組んできた賃上げですが、昨年末に組合員の署名協力のおかげさまで、昨年12月20日に妥結の運びとなりました。
新賃金は3月に改訂され、3月の給与支給分から適用されます。例年にない大幅な賃上げとなる一方、中堅層の賃上げ率抑制やRプランの影響による現給補償で、賃金が変わらない組合員がいる現実もあり、これから2025春闘をどう取り組んでいくかが課題となります。
【はじめに】
組合員の皆さま、日赤の施設に勤務されている職員の皆さま、日々の業務に追われる中で、日赤労組の運動にご協力いただき心から感謝申し上げます。
さて、2023年4月から新給与制度「Rプラン」に変わり、2年が経過しようとしています。制度導入後、各支部組合員からは、次のような声が寄せられています。
・現給補償を適用されているため、賃金が上がらずに生活が苦しい
・給与が直ぐに頭打ちになり、モチベーションが上がらない
・昇格の要件となる勤務評定がいい加減
・看護助手や福祉職などの職種では俸給表が他職種と比較して悪い
また、新給与制度とは直接関係はありませんが、ハラスメント関係の相談も増えています。もしかしたら勤務評定によるストレスも多少関係しているかもしれません。
【感謝の気持ち】
私は、来年の3月で定年を迎えます。今日まで血液センターを退職することなく過ごせたのは、職場の組合員、同僚、上司のおかげだと感じています。途中、仕事に行き詰まり抗うつ薬に頼らないと出勤ができないときもありましたが、周りのおかげで復活することできました。
最近は身の回りを整理することを始めました。生命保険や携帯電話料金等の見直しで数万円の節約になり、節約効果に驚いています。一方で、体力的な衰えも感じる中で、趣味であるスキューバダイビングをどのタイミングで〝潜り納め〟とするか、運転免許証の返納と同じ感覚で悩んでいますが、体力維持も日々欠かせません。週に2回ほどはジョギングを楽しみ、今は5kmを30分で走破しているので、あと3年はこのタイムを維持できるように走り続けます。
【春闘と新給与制度】
日赤における2024年の賃上げは、全職員平均3.58%(13,865円)と昨年の全職員平均1.31%(5,058円)と比較し、約2.7倍の引き上げとなりましたが、実施時期が11ヶ月遅れの2025年3月実施です。本社は、医療施設の大幅な赤字を主たる理由としていますが、物価高や賃上げ要求が4月実施を踏まえれば、4月まで遡及するのが本来の賃上げだと考えています。しかし、本社の3月改定を覆すことが出来なかったのは不満が残ります。
さらに日赤独自の問題として、俸給表の上限に達している職員は、ベースアップしても賃上げ額と調整給が相殺されて、実質は賃上げのメリットを受けられないのです。そのような職員が15%前後も存在していることにも注視しなければなりません。
連合は2025春闘方針で、生活向上分と物価高などを背景に昨年以上の「ベア3%以上、定昇込み5%以上」を掲げました。さらに2024年6月に改訂される診療報酬においては2025年のベアとして2.0%を含めています。よって、2024年6月には、ベースアップ評価料として7,000~9,000円が加算されたことを踏まえれば、2025年4月からは5,500~7,000円程度のベースアップ評価料が加算されるべきなのです。
ベースアップ評価料自体が、医療施設の一部職員しか適応されていないことも課題として残っています。よって、診療報酬とは無縁の血液センターや福祉施設で働く職員についても、上部団体のヘルスケア労協と処遇改善の取り組みを協議していきます。
また、2023年4月からスタートした新しい給与制度、特に俸給月額における格付けや昇格についても多くの課題があります。課題を克服するには、「制度の透明性を確保」して、そのうえで「公正な評価」が必要です。その為に私たちがすべきことは「制度の理解」が必須であり、組合員とのコミュニケーションを高めて、問題点の明確にして改善すべき運動の方向性を定めることが重要だと考えます。
さらに施設側への要求内容にも、上位に昇格するに必要なスキルと知見などを丁寧に教育していくことを要求することも必要です。スキルや知見等の向上は、組合員本人のためだけではなく、患者や献血者などの利用者にとってもプラスになることであり、施設にとっても高評価に繋がるからです。
【ヘルスケア労協】
私は本部中央執行委員長と併せて、医療福祉としての産業別労働組合の集合体であるヘルスケア労協の事務局長も兼務しています。日赤労組の運動とくらべて大きな違うところは、日赤労組以外の労働組合や組織と交流して情報交換や協働の取り組みをしている点です。
ヘルスケア労協の中心的な仲間は済生会病院の全済労や北海道社会事業協会の協病労組ですが、ヘルスケア労協は、自治労(地方自治体の市立病院、県立病院等)や全消協(消防職員の協議会)、日本看護協会、政党等と交流し、さらにヘルスケア労協が加盟している上部団体の日本労働組合総連合会の一員として活動もしています。
私たち医療福祉や血液事業の労働条件は、施設や本社との交渉で全て解決することは不可能です。病院の収入は〝診療報酬〟血液事業の収入は薬価(血液製剤)であり、それぞれ経営はこれらの影響を強く受けています。よって、労働条件の礎となる国の制度を、現場の声をもとに改善させていく取り組みが必要となります。改善を求めて厚労省などの国の機関に対して、日赤労組が単独で協議を申し入れしても「雇用関係は無い」と拒否されてしまいます。しかし、ヘルスケア労協や連合の一員として申し入れをすれば、業界の労働代表として国は話を聞く場を設けてくれるのです。
昨年は、医療供給体制における人員確保などを国に要請し、看護師確保や処遇改善について日本看護協会と情報交換を行いました。また、血液センターで働く労働者が、「血液の安定確保」のために長時間労働を強いられているという実態を連合に相談したところ、その連合を通じてヘルスケア労協と厚労省による協議の場として、厚生労働省の血液対策課と懇談会を設けることができました。即時、劇的な改善とまでは至りませんが、確実に前に進む運動が実現しています。引続き、多くの仲間たちと一緒に私も取り組んでいく所存です。
【PSIと平和】
ところで、一昨年の10月にヘルスケア労協の役員として私を含めて3名がPSI世界大会に参加するため、スイスのジュネーブに行きました。PSI世界大会は「パブリック・サービス・インターナショナル世界大会」と言い、世界の公共サービスで働く労働者の組合大会と位置付けられています。日本語では「国際公務労連」と称し、日本国内からは、ほかに自治労、国公連合、全水道、全消協が参加しています。
世界大会の討議で出てくるキーワードが「民営化」「平和」「医療福祉」「SDGs」です。世界で公共サービスの民営化が加速している中で、公共サービスだからこそ公正にできるサービスや新たな感染症対策と医療従事者の確保(処遇改善)、ジェンダー平等、そして重要なのは戦争反対ということ。紛争地域からの組合員報告では、多くのひとが傷つき亡くなっている現状が発せられていました。大会でも侵攻停止と、停戦の求める特別決議が満票で承認されることになりました。これらの討議は白熱し、私が経験したことがない真摯な訴えと議論がそこにあります。代議員が制限時間を超えて発言することにより、議長が発言停止を求めるようなこともありました。日本においては、戦後、大きな紛争に巻き込まれることなく、平和憲法のもとで生活をすることができてきましたが、一旦戦争がはじまると、普通の生活が一瞬で壊れ、憎しみが憎しみを生む負の連鎖が始まることを心に刻まなければならないと思います。
政府は諸外国からの圧力に対して防衛力の強化を進めています。国の2024年度の防衛費が16%増加と突出しているなかで「国を守る」ということは否定しません。しかし、守るべき国が先に衰退することは避けなければならない。教育や社会保障に予算を充て、人を育てることで外交力を高めることが、日本を守ることに繋がると考えています。
【団結してガンバロウ】
新型コロナウイルス感染症の影響により、5類に移行後も各支部における新規加入組合員のオリエンテーションなどが開催できずに組合員数も減少をしているのが現状です。根気よく運動を続けていく中で、仲間を増やしていく取り組みは必要です。辛いこともありますが、「日赤で良かった」「組合員で良かった」と言ってもらえる組織になるよう、本部・中央執行部一同で議論を重ね、組合の組織拡大強化に向けて頑張りたいと思います。
皆さんの声の繋がりが組合の強化拡大になります。仲間を増やし繋がり「日赤労組」を大きくし、職場環境の改善に向けて一緒に声をあげませんか。
日赤労組に相談の声を寄せ、ぜひ、加入してください。よろしくお願いします。
今年も団結してガンバロウ!